インフォメーション
INFORMATION
- INFORMATION
- 油外放浪記 第202回「年間利益5000万円のSSフオーマットが完成」
2025.08.10
油外放浪記 第202回「年間利益5000万円のSSフオーマットが完成」
6月不調の要因を店長が除去
当社の会計年度は、第39期が6月で終了し、7月から第40期が始まっています。
今回の油外放浪記は、第39期の年間実績を総括しつつ、SSというビジネスモデルの可能性を考えます。
その前に、いつものように6月の実績を振り返ります(表1) 。
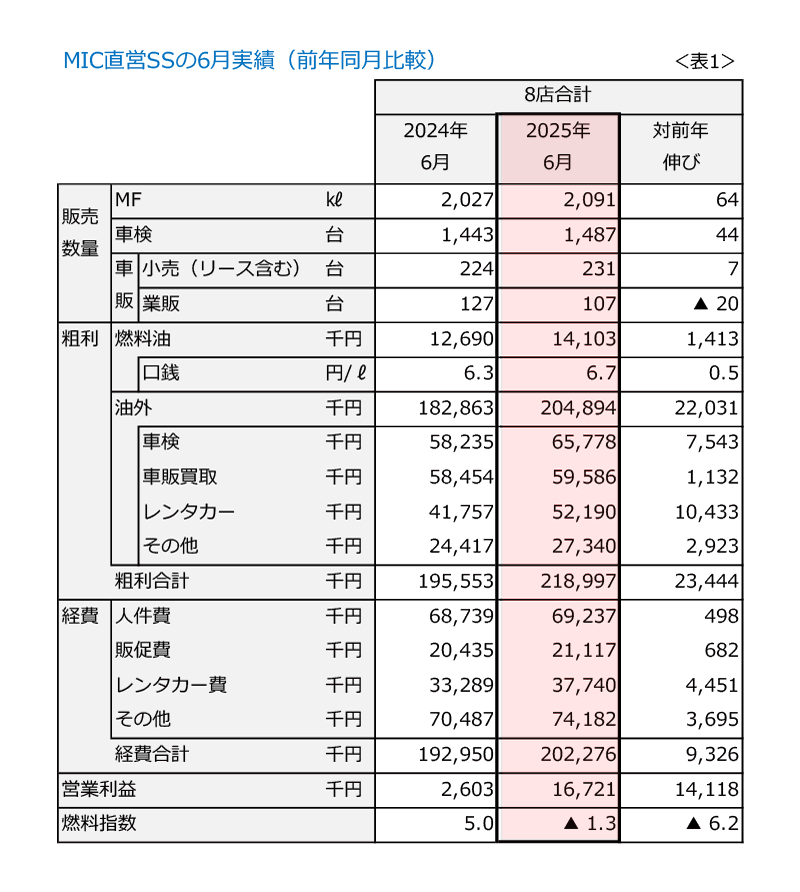
営業利益は、前年同月比1,400万円増の1,670万円(8店合計)。前年が悪すぎたと言われればそれまでですが、例年、6月は悪い条件が3つ重なるのです。
(1)主力商材の需要が落ち込む
当社のSSの重点商品は、車検、車販、レンタカーです。しかし6月はいずれも需要が冷えます。
(2)店長の下心
期末ともなると、目先の実績はほどほどにして、来期の数字を作っておきたいという心理が働きがちです。
(3)有給休暇の泥縄式取得
働き方改革の一環で、年5日以上の有給休暇を取得することが義務づけられました。例年、期末になって強制的に消化させることとなり、販売担当者が不足します。
(1)はともかく、(2)(3)は店長の心掛け次第です。今年こそは例年の轍を踏むまいと、従前から店長ミーティングで繰り返し強調したのが奏効しました。店長が営業利益を1,400万円改善したということです。
燃料油の販売量は、かろうじて前年を上回りました。世の中の減販基調に逆らい、前年並みを維持しているのは「良し」としましょう。
油外収益は2,200万円増の2億円。重点商品が3品とも前年を上回り、6月の最高値を更新しました。
インバウンドのレンタカー需要がうなぎのぼり
レンタカーの収益性が高いのは、「SSとの兼業」を前提としたビジネスモデルだからです。
既存の人、店、設備を活用しますので、損益分岐点が極めて低い。したがって利用料金を半額にしても、売り上げの半分が利益となります。
これほど高収益安定ビジネスは、滅多にありません。もっとお店を増やしたい。しかし当社には、直営SSが8カ所しかありません。本当に口惜しい。
ならば、専業の店を出してみようか、と出店したのが2010年。やはり店の家賃や人件費が重くのしかかり、ほとんど利益が出ません。
それでもあきらめずやっていくうち、空港立地で100台以上の車両を運用すれば、私たちのビジネスモデルでも成立することが分かってきました。そこで全国の空港を調査し、レンタカー営業所を開設できる場所を地道に探してきました。
こうして新千歳空港店、成田空港店、福岡空港店など6カ所のレンタカー専業店を出店してきました。
ほとんどの空港は、周辺に人が住んでいません。これがSS立地と大きく異なる点です。そう、空港前レンタカーのターゲットは、地元客ではなく空港利用者、つまり、遠方からいらっしゃった観光・ビジネス客です。
ところが2020年、コロナ禍による行動制限で、空港利用客が突然消滅しました。前記6店の仕事がなくなってしまったのです。店は休業、アルバイトは自宅待機とし、店長たちはレンタカー車両を売りさばくため、本社に転勤させました。
この組織が、今の車販ビジネスを下支えするようになったことは、これまで本稿で述べてきたとおりです。
さて、コロナが終息しつつあった2022年頃から、空港レンタカー店を再稼働しました。
すると、無視できない数のインバウンド客(外国人観光客)のご利用が発生するようになりました(グラフ1) 。
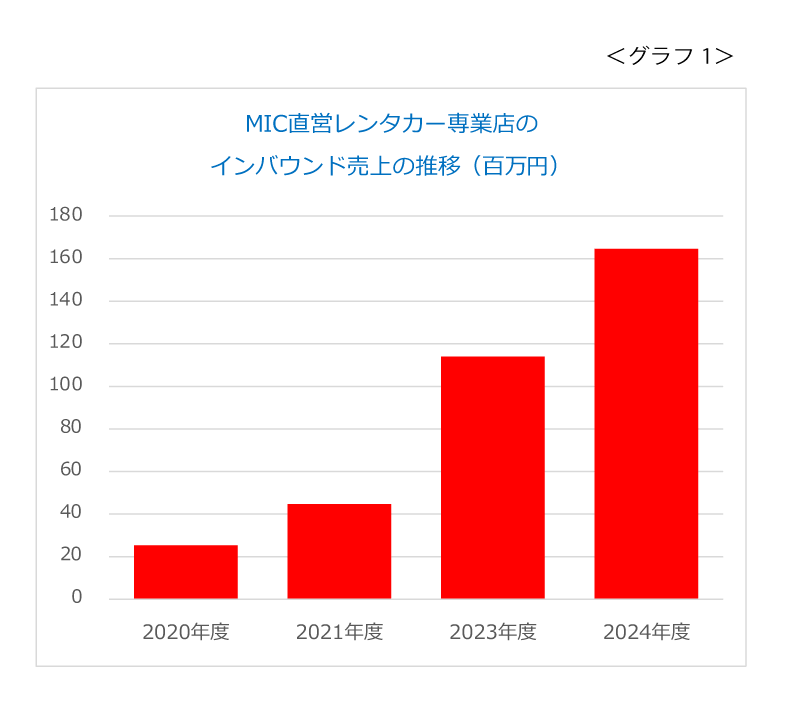
オープンデータを調べてみました。インバウンド客の入国数は、年間3,700万人。うち、レンタカーの利用は3.7%(国土交通省) だそうです。つまり、年間130万人が国内の空港でレンタカーを借りています。
国内のレンタカー市場は8,200億円、このうち740億円(9%) が、インバウンド需要と言われます。当社のインバウンド売上は1.6億円なので、シェアは0.2%です。
今年に入って、たて続けに関西空港店(6月) と羽田空港店(7月)を新規オープンしました。市場シェアをどこまで伸ばせるか、期待が膨らみます。
SSが過去最高益を出す
当社のSSの先期(第39期)の年間実績を(表2) に示しました。
ポイントを3つ挙げます。
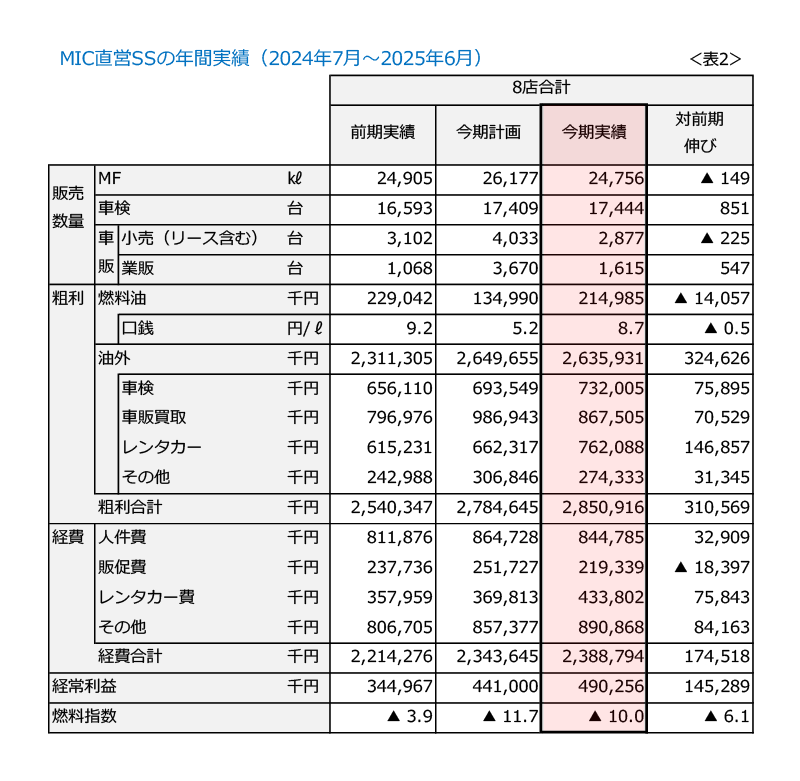
(1)利益
年間経常利益は4.9億円でした(8店合計)。
計画を5,000万円上回り、前年比は1.4倍の成長です(なお、タイヤメーカーからの報奨金などを繰り入れましたので、経常利益を見ました)。
1店当たり6,100万円の利益です。とうとう「5,000万円」を超えました。
8店中6店は他社から運営を引き継いだ店です。「普通の商圏、普通の立地、普通のSSで、年間5,000万円以上の利益が上がるビジネスモデルを作り上げたい」という10年来の悲願が、現実となりました。
もちろんSS別に見ると(表3) 、下は小田原東IC店から、上は仲町台店まで、店舗規模や商圏特性によって違いは生じます。しかし、全店とも前年を大きくクリアしたのは立派です。
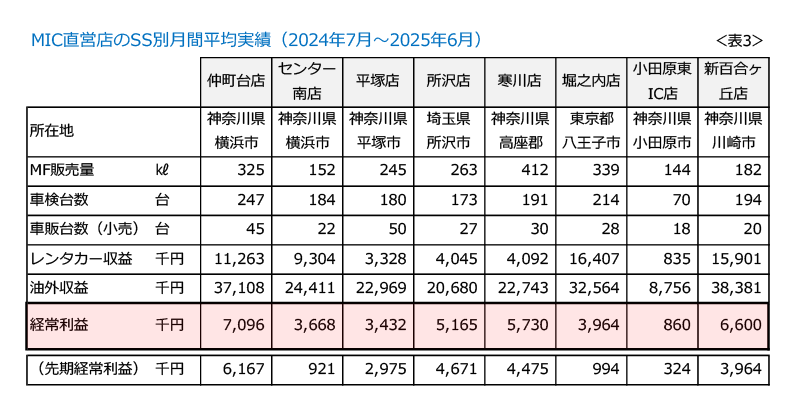
私たちは、試行錯誤(油外放浪)して10年かかりました。しかしもう、やり方は分かりました。
もしも住宅地の生活幹線道路に立地する300坪以上のSSであれば、中古車仕入れやコールセンターなど、サポート部門も活用するとして(もちろん応分をSSの経費に計上します)、3年あれば到達できるでしょう。
(2)油外
粗利益は、燃料油が1,400万円減少しましたが、油外が前年比3.2億円増加し、26億円です。
月間平均2.2億円となりますが、この12カ月間、一度も2億円を下回らなかったのは、アッパレ。季節に左右されず安定的に販売できるようになりました。
1店当たり月間の油外粗利は2,700万円です。この数字は、おそらく国内ではトップクラスではないでしょうか。
私が若い頃、SS店長向けの通信教育講座を担当させていただいたことがあります。そこでは元売会社の方針に沿って、燃料油販売100kl、油外粗利200万円、すなわち「L当たり20円」を、目指すべきSSモデルとしていました。
しかし私は、当社MICを創業してからずっと、SS経営者の方々に「油外100円/LのSSを作りましょう」と、一生懸命訴え続けてきました。
「何を浮世離れしたことを…」と呆れ顔をされたものです。
しかし気がつくと今、当社の油外収益は、L当たり106円です。まだまだ課題はあるものの、車検、車販、レンタカーを中核とした油外販売の基本形が出来上がったと見ていいでしょう。
特にレンタカーの伸びが著しいのが目を惹きます。この1年間で車両費を7,500万円増やしましたが、収益は1.4億円増加しました。
車検は前年実績、計画値ともにクリアしました。台数の伸び率は105%ですが、粗利は同112%。台数の伸び以上に粗利が伸びたのは、客単価が上がったからです。
車販は「小売り」の落ち込みを「業販」がカバーしました。さりとて、業販は「打出の小槌」ではありません。小売りの復興(あるいは革新) が望まれます。
(3)経費
かつて経費は、前年比120%が当たり前のことでしたが、108%に抑えられました。ここ3年間、新規出店投資を控えたことが一因です。
そして、先期は「労働生産性」の向上を重点テーマの一つとしました。
毎週の店長ミーティングで口うるさく言い続けました。さしもの店長たちも、生産性の目標と現実の乖離を意識するようになり、工夫し始めます。
たとえばー。
●油外販売のコアタイムは10~19時ですが、その時間帯に配備する社員の比率を高めました。
●事前に店長に申請しなければ残業させない、つまり理由のない残業を廃止しました。
●これまで整備士のシフトに合わせて、車検や定期点検の受け入れ枠を決めていましたが、受注量とシフト配備を完全一致させました。
●車検だけでなく、すべての商品の単価を見直しました。
●生産性の合わない商品、たとえばコーティングの販売優先順位を大きく下げました。
●店独自の広告掲示物を廃止し、掲示場所やサイズを標準化し、本部から一斉供給するようにしました。
●店の清掃は、業者に外注しました。
どこまで徹底できたかはつかめていませんが、結果は明瞭、人時油外粗利が1年間で600円改善しました(表4) 。これこそが、ベースアップの元資となります。
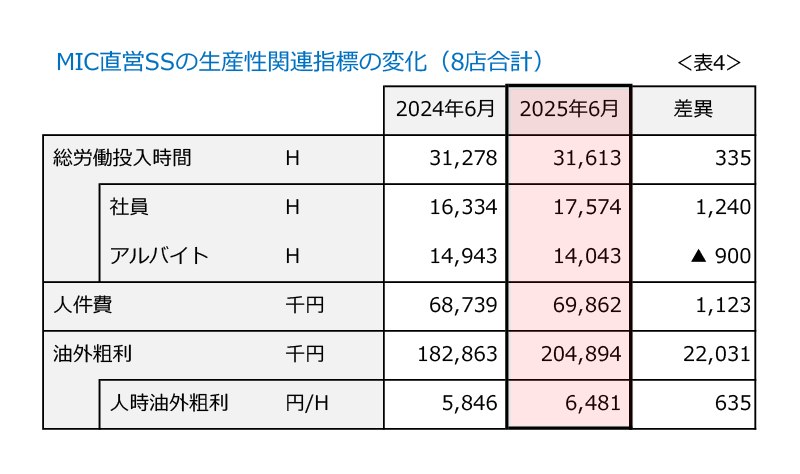
誤解のないよう申し上げますが、私はコストを使うことに対して、あまりうるさく言いません。「やってみなさい」と激励するタイプです。
ただし、「使ったお金の最低2倍は稼げ」が合言葉。先期はどうだったでしょうか。(表2)を見てみましょう。
経費は前年比1.7億円増加、対して油外粗利は同3.2億円増加。うーん、2倍には届きませんでした。
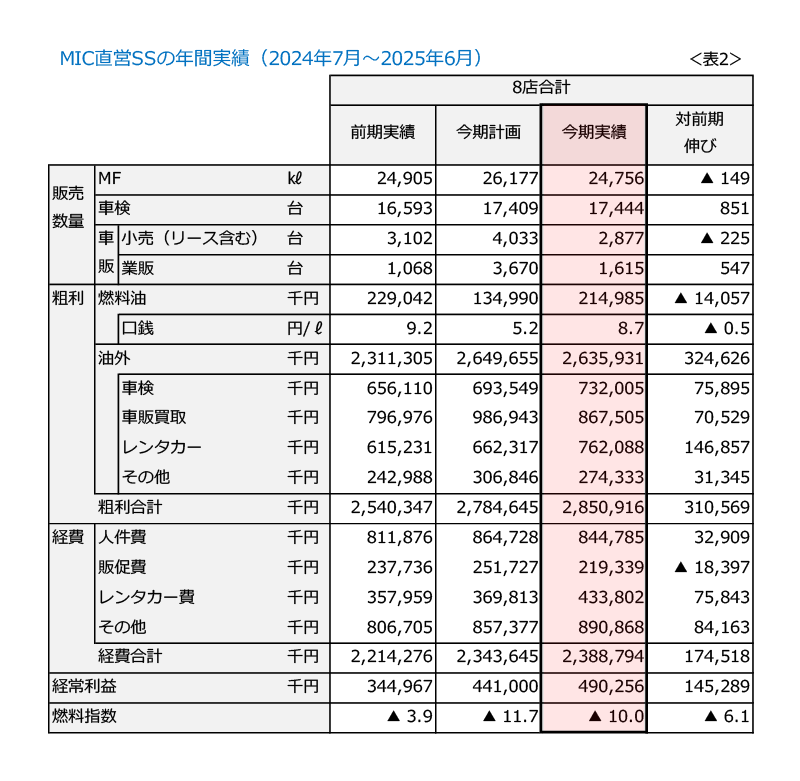
SSスタッフの地位向上に貢献したい
さて、当社は40期目に突入しました。このうちSSの運営歴は、30年となります。何とか淘汰の荒波に逆らい、生き残ってきました。
そして、直近10年で「営業利益5,000万円」を実現しました。
さあ、次の10年、果たして世の中の変化についていけるでしょうか。
かねてから私は、SSで働く人の社会的地位の低さを嘆き、スタッフ自身が自らの職業を卑下するような風潮を打ち破りたいと切望しています。まずは店長以外のSS社員の平均年収を、上場企業を上回る700万円にすることが目標です。
生産性をさらに改善していくしかありません。


