インフォメーション
INFORMATION
- INFORMATION
- 油外放浪記 第198回「SSにこだわってきた40年。だが、こだわりきれなくなってきた」
2025.03.10
油外放浪記 第198回「SSにこだわってきた40年。だが、こだわりきれなくなってきた」
油外販売体制はほぼ完成
いつの間にか3月(原稿執筆時点)。時の過ぎるのが早いと感じます。
当社のSSの2月の数字がまとまったので、(表1) に示します。
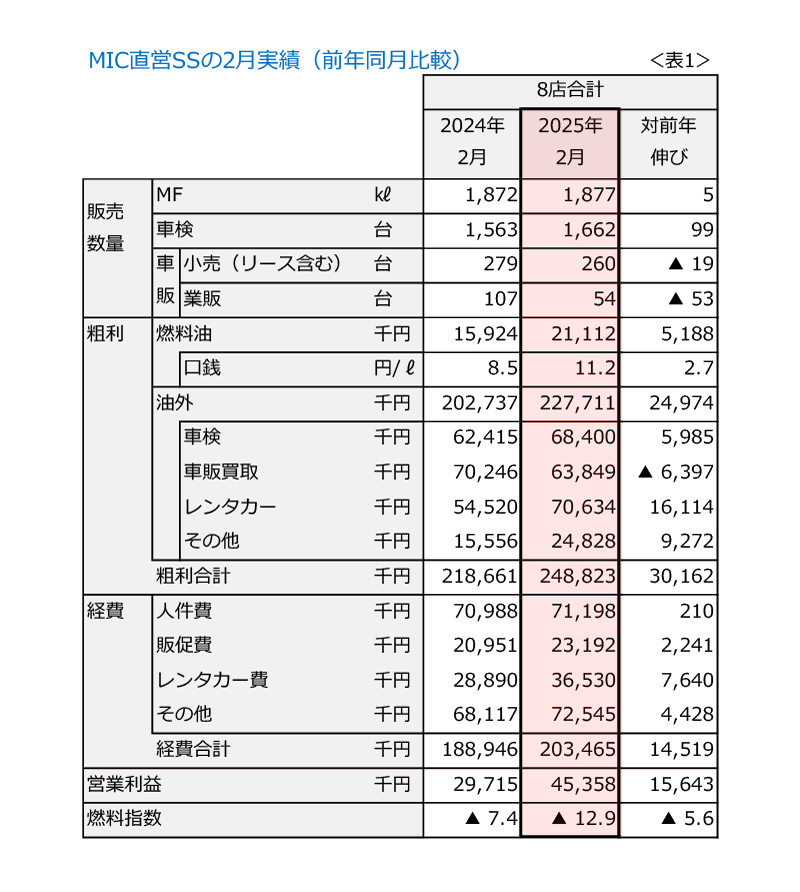
営業利益は、前年より1,500万円増加し4,500万円(8店合計)。2月も月次最高値を更新しました。
燃料油マージンが2.7円も上昇したのも嬉しいことですが、油外粗利2億円超えが、すっかり定着しました。
当社が主力に据える車検、車販、レンタカーについては、販売手順がほぼ整ったと見ていいでしょう。所定の行動手順を徹底すれば、結果につながります。
決定したことを確実に実行するための管理体制も強化しました。しかもこの3年間、SSの新設など大きな投資もなく、マイナス要因がなくなりました。
車検はリピート率と販促費のバランス
毎年1~3月に実施する車検キャンペーンは、中盤戦。
2月までの累計実績は、目標3,157台に対し、実績3,127台。30台足りません(1店当たり4台)。3月に挽回できるかどうか。
2月から車検基本料金を値上げしました。ながらく「1万円ぽっきり」を謳ってきましたが、1万3,000円にしました。今のところ大きな影響はないようで、胸を撫で下ろしています。
今、あらゆる物価が高騰しています。車検で3,000円の値上げは、顧客にとって許容範囲内と言えそうです。
そうそう、経費と言えば、電気代、水道代が100万円も上昇していると知り、びっくりしました。洗車も値上げすべきでしょうか。精査する必要がありそうです。
さて、当社が車検に取り組み始めたのは1995年。第1号仲町台店のオープンと同時です。
得意とする「販売促進」を駆使し、当初から月間200台以上の入庫を実現してきました。しかし、恥ずかしながら「リピート率」という概念を知りませんでした。
やがて、世の中の優秀な車検工場は、75%以上のリピート率を維持していると知りました。流出する25%以上を埋めるため、販売促進費をかけ、新規客を取り込んでいるとのこと。
さっそく当社のリピート率を調べてみました。何と30%。どおりで販促費がかかってきたわけです。
新規客を獲得し続けないと激減するので、販促費は絶対に必要。同時に、リピート率を改善し、販促費を抑える努力も必要だということです。
すぐに改善できるだろうと、タカを括っていました。ところが、やきもきするほど上がりません。なまじSS業態は、オープンな店構えで入店の敷居が低いので、顧客の流動性が高く、車検もなかなか定着してくれないようです。
それでもあきらめず、長い期間をかけ、ようやく60%台に到達しました(グラフ1) 。
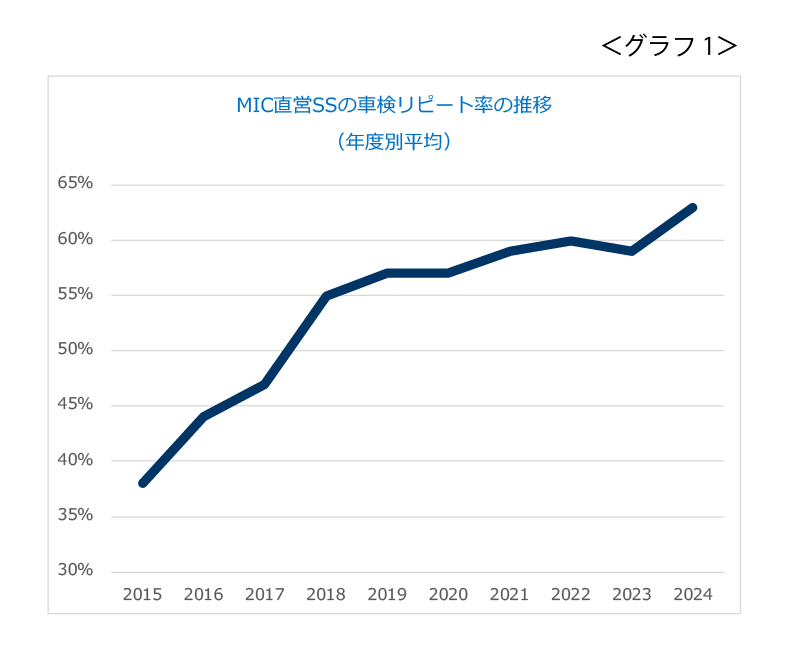
リピート率を高める主要指標として、Googleの顧客評価(GBP) に注目しています。5点満点中、最初は3点くらいでした。今は4.23点(8店平均)。そして、車検入庫1台当たり販促費(CPO)は1万700円となっています。
レンタカーもリピーターが安定収益をもたらす
次はレンタカー。
一般的にレンタカーは、シーズン変動の高い商品です。最需要期は8月で、3月から春夏にかけ高くなります。9月のシルバーウィークまで高需要は続き、秋冬は冷え込みます。
レンタカーは、車両償却費と保険税金が経費のほとんどを占めます。そこでこれまでは、秋冬はレンタカー台数を減らし、利益を確保しようとしてきました。車検や洗車は需要に合わせて設備を拡大・縮小できませんが、レンタカーは簡単にできます。
しかし今期はあえて減らしませんでした。するとどうでしょう。昨年2月は514台で売上5,452万円、1台当たり10万6千円。今年2月は654台で7,063万4千円、1台当たり10万8千円。むしろ活性化したではありませんか。
(グラフ2) を見ると、12月以降、増車して経費が増えましたが、これを上回る売上が上がり、利益が増えたことが分かります。
地域に密着するSSレンタカーは、旅行・観光需要に頼りません。地元の生活者の反復利用を主ターゲットとします。その累積が、シーズン変動を緩和し、安定ビジネスヘと導いてくれます。
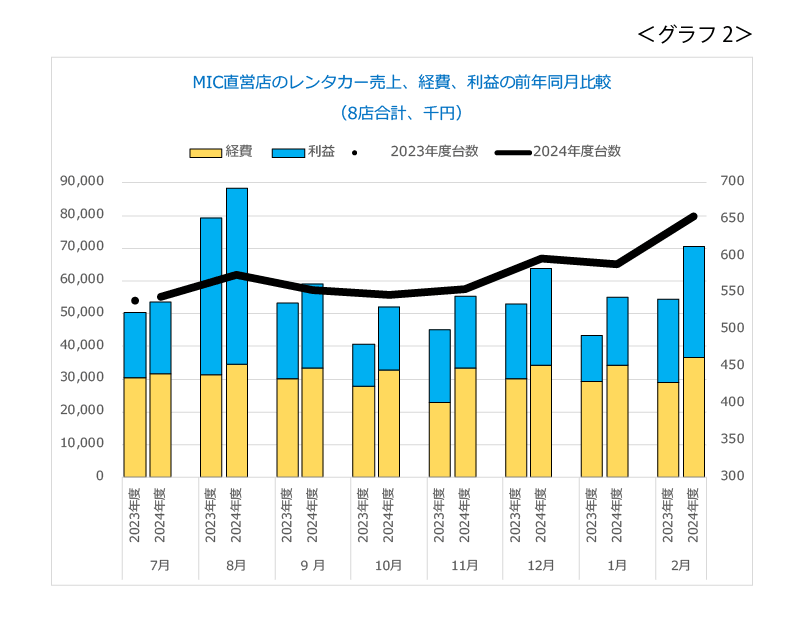
車販は深掘りステージに入った
車販の伸びが止まりました(グラフ3) 。
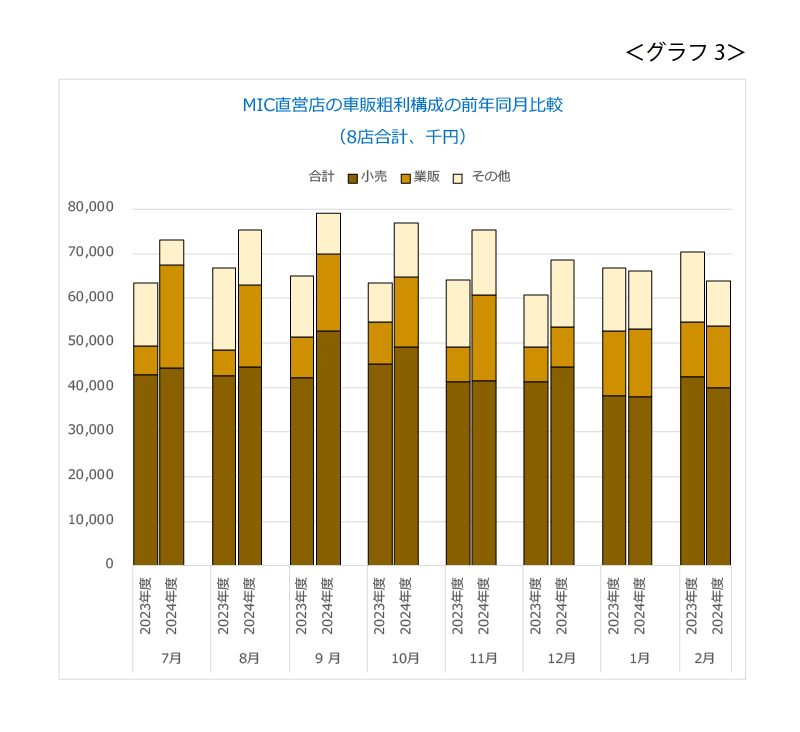
「小売り」は1月に前年割れ、2月はさらに落ち込みました。「業販」も12月から伸びが止まりました。
今後の業績改善の「旗頭」と考えていただけに、ショックです。
当社にとって車販は古くて新しい商材。突破口を見いだすため、広く試行錯誤を行なってきました。が、車検やレンタカーのように深掘りしていないので、ノウハウの厚みがありません。
伸びを阻害する要因に真正面から取り組み、何回か乗り越えれば、車販も盤石になるでしょう。思いつく課題は、競合の研究、商品力や販促の強化、販売手順の標準化とマネジメント、評価基準、顧客管理やアフターフォロー、といったところでしょうか。
環境変化に食らいついてきた40年
私は、これまで「SSというプラットフォームを活用した油外販売」にこだわってきました。しかし、そろそろ限界を感じています。
「月刊ガソリン・スタンド」誌の原稿としては馴染まないかもしれません。しかし今後は、SS以外で当社が手を広げようとしている新事業についても、情報を開示しようかと思います。
その前に、当社MICの創設から40年間、経営環境の変化に対応して3回の大きな体質転換を行いました。その経緯を振り返っておこうと思います。
ガソリン販促のMIC
私は学校を卒業して、マーケティングリサーチ会社に勤務しました。そこで学んだのが、小売業の集客手法です。一方、当時、ガソリンスタンド業界は掛売りが主流で、現金客は軽んじられていました。
そこで1986年に独立した私は、折り込み広告と景品で集客し、現金客を会員化、DM(ダイレクトメール)で反復利用させるという手順を提唱し、ガソリン増販に劇的な効果を出すことを実証しました。
この噂が噂を呼び、たくさんのご依頼をいただきました。海外へ長期社員旅行するなど、会社はバブルに沸きました。
この方法はその後、あらゆる元売会社が現金会員カードを発行するきっかけともなりましたが、次第にMICは「モノクレ」販促の元凶と椰楡されるようになります。本当に、ずいぶん非難されました。
やがて、モノクレ集客や会員管理センター機能が元売会社に標準装備されてしまうと、MICへの仕事の依頼件数は激減しました。
そこで当社は、ガソリン増販から油外販促へと路線変更します。
当時の油外販売で知られたSSの販売方法は、給油中にボンネットを開け、アラを探し、押し売りするというやり方でした。
お客様からしたら、大迷惑。そこで当社は、ガソリン増販と同じやり方、すなわちチラシを撒き、景品をつけ、お客様が買いに来てくださるのを待つ、というやり方を、懇意にしていただいたSSで試してもらいました。
ところが、まったく売れません。洗車もオイルもタイヤも、一通り試しましたが、お客様はまったく反応しません。
かくなる上は、自らSSを持ちたい。油外販売の方法を思う存分、あれもこれも試したい。そう決心するに至ったのです。
ご協力いただける元売会社を探して3年、晴れて、仲町台店(神奈川県横浜市) のオープンに漕ぎ着きました(1995年)。
ガソリンは月販800klを売り、面目を保ちました。そして、温めてきた方法を片端から試し、ことごとく失敗しました。が、洗車と車検に光明を見いだしました。
給油時の声掛けを徹底すれば、洗車はL当たり10円売れました。車検は販促が効きました。1996年3月の入庫416台という記録は、いまだ破られていません。
車検コンサルタントのMIC
1996年は、特石法が廃止された年でもあります。どのSSも燃料油口銭が失われ、ガソリンに販促費をかけない時代となりました。当社には当時、社員が100人くらいいましたが、半数が見限り去って行きました。
残ったのは、50人くらいのスタッフと1カ所の実験店、そして洗車ネタと車検ネタ。
ただ洗車は、人件費がかかりすぎ生産性がよくありません。そこで、車検に重点を置くと決めました。仲町台店で破天荒な数字をたたき出し、全国のSSに発信しようではないか。背水の陣で臨んだ結果、「車検を教えてほしい」というご注文が舞い込むようになりました。
ほっと一息ついたのも束の間、1998年、SSのセルフ化が解禁されました。
全国のSSが、雪崩をうってセルフ化していきます。給油中にフロントガラスのステッカーを見て、声掛けするという販売方法は、やがて通用しなくなりました。
そこで取り組んだのが車番認識システムの開発です。機械が声掛けすべき対象客を見つけてくれるという仕組みです。かなりの費用を投入して開発したにもかかわらず、セルフSSの省人化の波は止まりません。車検を売るにも作業するにも、人手が足りないという理由から、石油販売業界で普及するには至りませんでした。
したがって、会社の収益がジリジリ下がるのを食い止めることはできません。
SSレンタカー事業を開発
次に取り組んだのが車販です。
2004年、オークションの落札代行(オークション・ダイレクト) を始めたのはいいものの、どう頑張っても月間販売台数5台。これでは焼け石に水。そろそろキャッシュも底を尽きてきました。新規投資ができないばかりか、本当に首が回らなくなってきました。
そんな折、SSに「廃車・不要車1万円で買い取ります」という看板を掲げたところ、月50台くらいの廃車が手に入るという現象が起きました。
そこから年間3,000万円くらいのキャッシュが生まれたので、少し余裕が出ました。それだけではありません。買い取った不要車の中には、まだ十分に走る、このままスクラップ(処分) するのはもったいない、という車が散見されました。
2008年、格安レンタカーの誕生です。
当時、当社の運営するSS数は4カ所でしたが、どこでやってもバカ売れ。この事実をSS業界に向け発信したところ、翌年からフランチャイズ・チェーン(FC) 展開することになりました。その後も紆余曲折はありましたが、これが今日の当社の屋台骨となっています。
700人の食い扶持を守りたい
2020年、突然コロナが襲来しました。空港前に出店していたレンタカー直営店は、軒並み閑古鳥。500台の車と十数名の人員が、稼働しなくなりました。
ダメモトで、余剰人員を寄せ集め、余剰車両を中古車検索サイトに掲載してみたところ、たちまち完売しました。
すぐにプロジェクトチームを結成。今度はオークションから中古車を仕入れ、中古車サイトに掲載し、SSに在庫。すると顧客から問い合わせがあり、SSが売る。この流れをつくったところ、年間4,000台の中古車が売れる規模まで成長を遂げました。
こうして当社は、ガソリンスタンドの顔をしながら、その実は、車検、車販、レンタカーを営む企業となりました。社員数250名、アルバイトを含めると700人の所帯です。
これを今、脅かしているのが「カーボンニュートラル宣言」です。
当社の事業はすべて「ガソリンで動く乗用車」ありきで存立しているわけですが、2035年には、世の中すべての車両を電動車にしますよと、こともあろうか、わが国の総理大臣が発表したものだから、さあ大変。
ガソリンとは無縁な事業開発に取り組まざるを得なくなりました。
余命あと10年です。ガソリン車が生きているうちに、可能な限り稼いでおきたい。その一方で、新事業開発にも投資しつつあるところです。


