インフォメーション
INFORMATION
- INFORMATION
- 油外放浪記 第197回「お客様から選ばれる油外商品を作りたい」
2025.02.10
油外放浪記 第197回「お客様から選ばれる油外商品を作りたい」
稼げるときに稼いでおこう
EV(電気自動車) の世界販売台数が、前年割れし始めたとのニュースが飛び込んできました。バッテリーのコストダウンが予想以上に難しいそうです。各国の補助金も尽き始めたようです。相対的に、ハイブリッド車の需要が高まっていると聞きました。
もしかしたらカーボンニュートラル社会の到来が、少し遠のいたかもしれない、と密かに期待しています。
当社のSSの1月実績を見てください(表1) 。
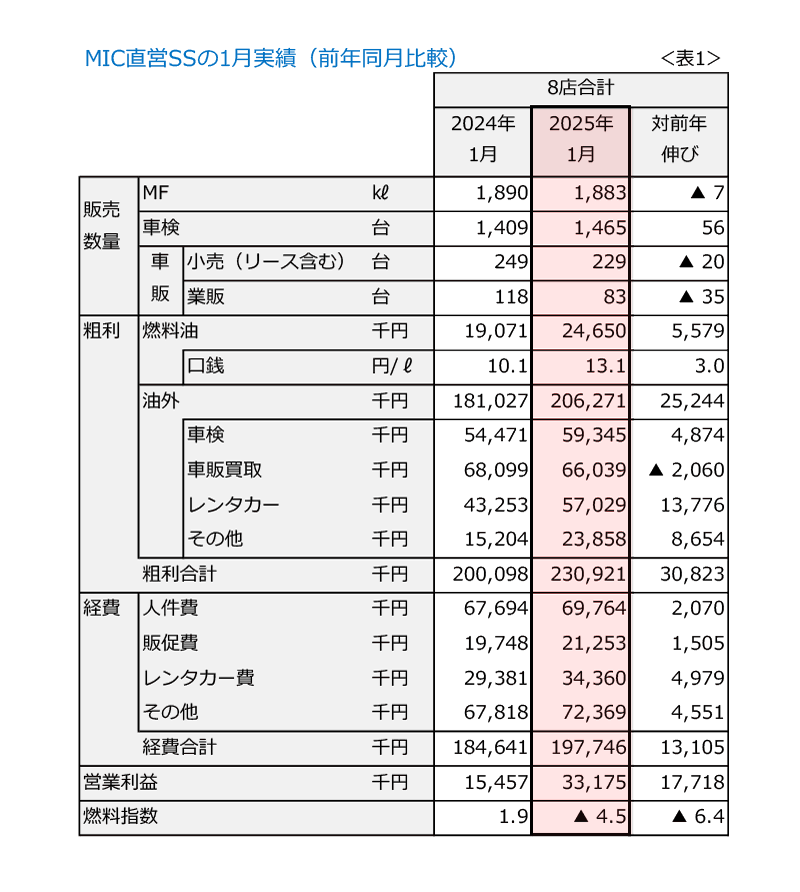
燃料油販売量の減少が止まったかもしれません。なんだか気持ちが明るくなるのは、昭和世代のSS店主の性でしょうか。
営業利益は、3,300万円(8店合計)。前年同月の2倍以上を稼いでくれました。経費がやや増加しましたが、油外粗利が3,000万円増。何と56カ月連続して、前年同月を上回り続けており、今や「油外2億円超え(8店)」が常態化しつつあります。
いずれにせよ、カーボンニュートラル社会が本格化したときの備えを、今は既存の商材で、稼げるだけ稼いでおこうと思います。
車検とレンタカーは絶好調 車販がマイナス
今年も1~3月は車検拡販キャンペーンを実施し、販売活動に弾みをつけようとしています。
昨年は目標に到達できませんでした。この無念をはらそうと、全店気合い十分です。
1月までの結果を(表2) に示します。台数は目標に17台足りませんでした。粗利は昨年夏から客単価をテコ入れした(後述) ことが効いていますが、まだ油断できません。
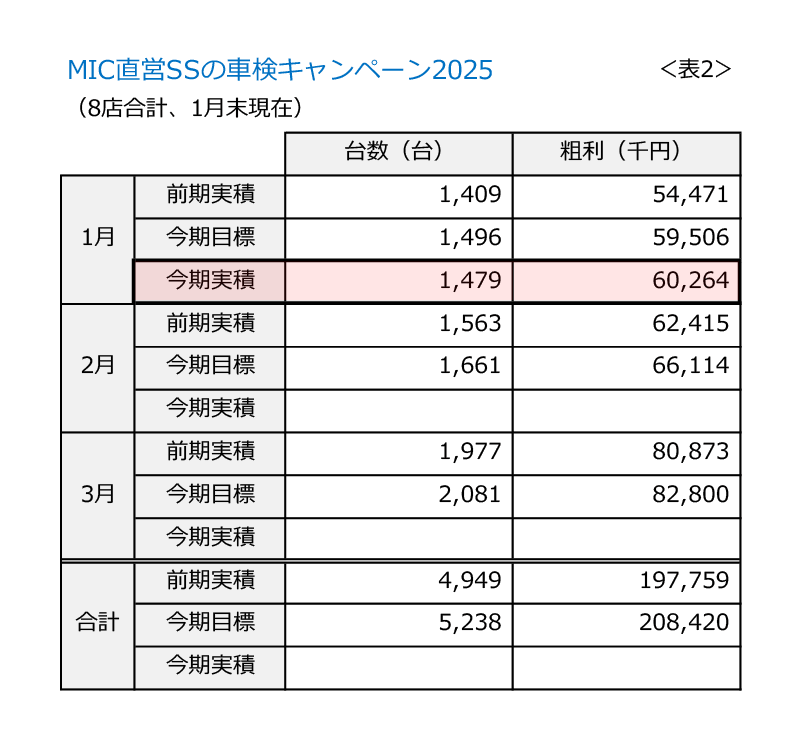
次にレンタカー。
1月は1,300万円増加しました。増車と商品力強化の効果です。例年、11月から2月はレンタカー需要が冷え込むので、レンタカー台数を減らしていました。しかし今年は敢えて増車し、車種の構成も見直しました。つまり「台数の増加×台当たり売上の増加」ダブルの効果が出た、というわけです(グラフ1)。
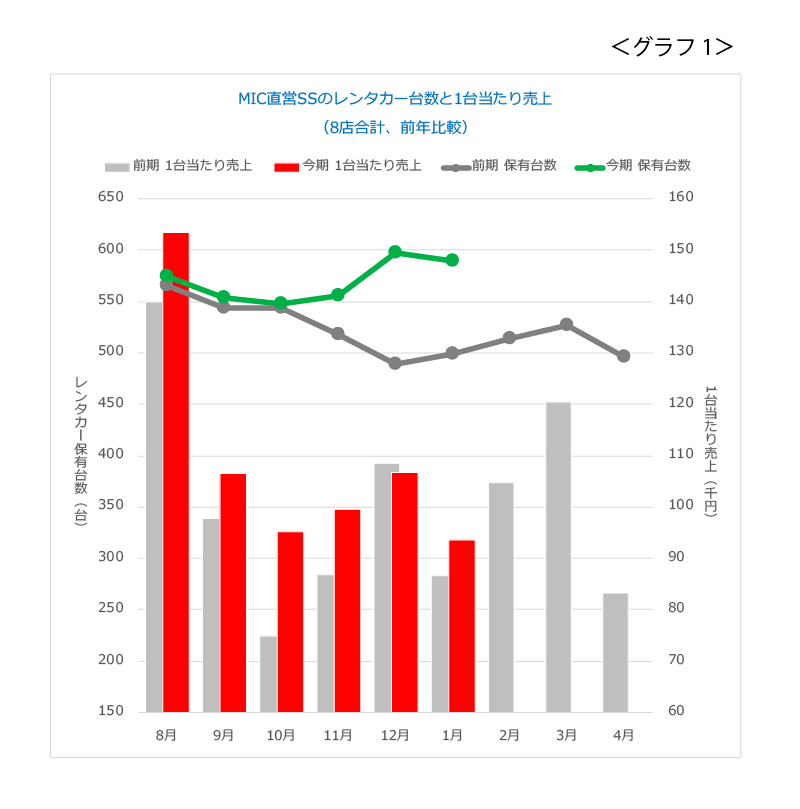
オフシーズンの売上を支えてくれるのが、リピーターすなわち日常利用客の存在です。地域密着型SSのレンタカービジネスの大きな強みです。
グラフを見ると、今年は1台当たり売上の振り幅が緩和されたことが分かります。リピーターの増加に台数の増加をうまく合わせられたのではないでしょうか。
さて、車販です。
とうとう前年割れしました。以前に述べたとおり、車販担当者への個人インセンティブを廃止した途端に伸びが止まり、ここにきて減少し始めました。
理由を聞くと、異口同音に「ウィーカーズ」と言います。ご存知のとおり、ビッグモーターを買収した伊藤忠商事が、新たに設立した中古車販売チェーンです。さすが大手企業。地に落ちた悪評でしたが、早くも払拭され始めたのでしょうか。
SSレンタカーは「バカ安」で勝てる
マーケティング用語で「USP(Unique Selling Proposition) 」というものがあります。
自社の商品サービスにしかない独自の強みを言います。つまりはお客様が、なぜ他店でなく自店で買ってくださるのか、その理由づけです。
当社の重点商品は、車検、車販、レンタカーですが、それぞれにUSPを意識してやってきました。
最も強くUSPを打ち出すことができたのが、レンタカーです。
2008年に「ニコニコレンタカー」という独自ブランドで参入しました、翌年からFC展開を始めましたが、最初は右も左も分かりません。しかし10年もやっていると、収益化のポイントが分かってきました。
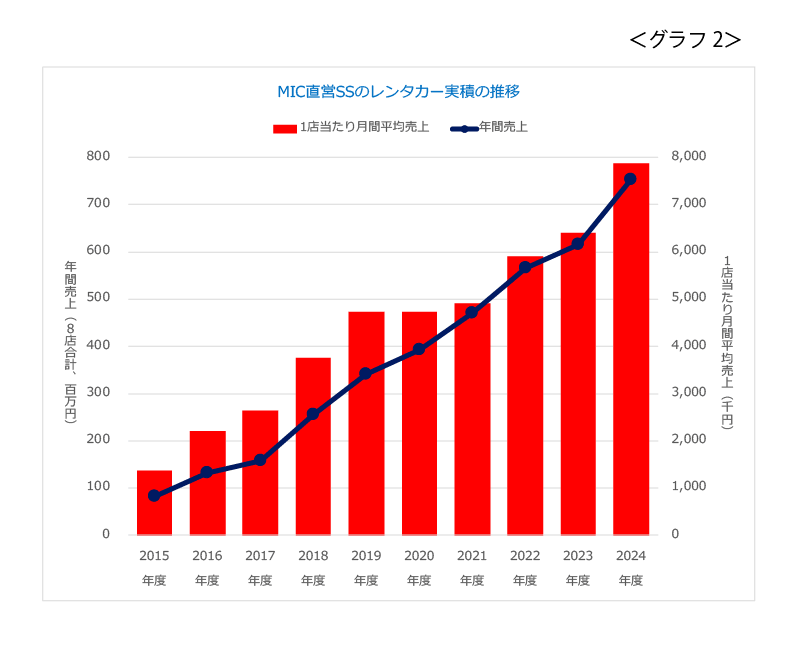
連戦連勝爆進中です(グラフ2) 。コロナ禍も無難に乗り切り、今期の収益見通しは7.5億円。
レンタカーの顧客ニーズは、「高品質」「低価格」「利便性」の3点です。接客レベルや車種の豊富さ、乗り捨てサービスといったニーズも確かにありますが、この3点には及びません。とりわけ「低価格」としたことが、SSレンタカービジネスの圧倒的なUSPとなりました。
トヨタレンタカーやニッポンレンタカーの半額。「バカ安」と言っていいくらいの、強力な訴求力を発揮します。マスメディア広告を一切しなかったにもかかわらず、15年で、日本人の2人に1人がブランド認知してくれるに至っています。
そして「バカ安」であることは、レンタカーの日常利用という、新しい使い方を生み出しました。15年前は「車離れ」というキーワードが世の中に出た頃でしたが、今や当たり前のライフスタイルとなりました。
では、なぜ「バカ安」なのに、利益が売上の半分程度残るのでしょうか?
SSとの兼業だからです。店舗設備費や人件費がかからないため、1台当たり経費は5万円弱に収まります。損益分岐点は大手レンタカーの半分。彼らが逆立ちしても真似できない圧倒的なUSPは、SSとの兼業であることによって生み出されるわけです。SSレンタカーは「薄利多売」と思われがちですが、実は「厚利多売」のビジネスモデルだったのです。
いやいや、安い中古車を使っているから安いんじゃないの?と思う方もいらっしゃいます。
私たちも最初はそう考えていました。しかし、やってみて分かったことは、メンテナンス費や償却後の車両価値(リース残価)を考えると、実質的な車両原価は、新車も中古車も、ほぼ変わりません。
むしろ新車の方が、点検整備や事故、故障、クレームにともなう手間が激減し、顧客満足度も劇的に向上、かつスタッフの精神衛生上も良いのです。
当社のSSは600台近いレンタカーを運用していますが、平均車齢は1.5年。大手レンタカーと比べ、「品質」は遜色ありません。「
価格」は半値、そしてもともと地元客に便利なSS立地で、営業時間も長いですから、「利便性」も申し分ありません。
・・・というわけで、SSレンタカーが大手レンタカーに負けるわけがないのです。
SS車検は競合の弱さを突くことで競争力を維持
次に、かろうじてUSPを付与できているのが、車検です。
過去10年間の、当社のSSの車検台数の推移を(グラフ3)に示します。
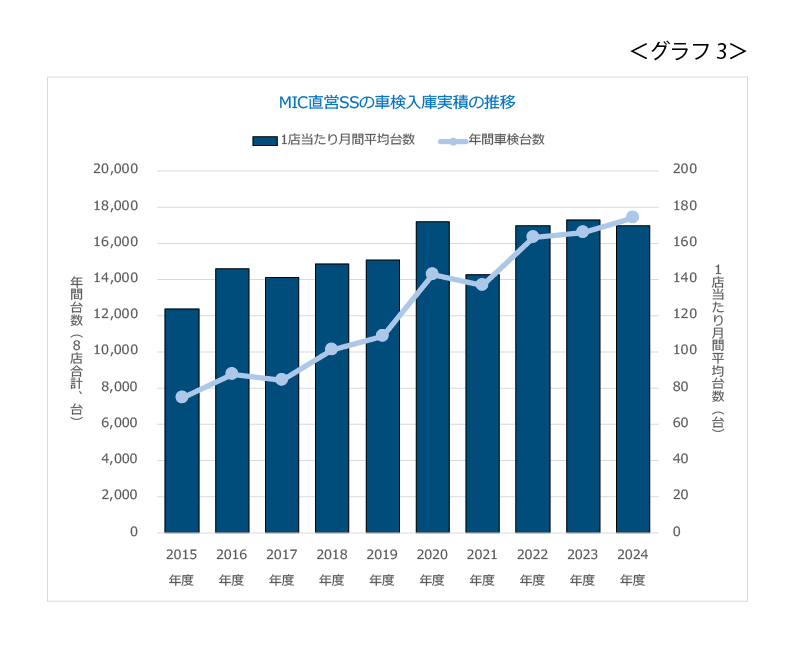
1店当たり月間平均台数は、170台で頭打ちとなりました。これは処理台数すなわち、設備キャパシティの制限によるものです。
しかし店を増やした分、年間車検台数は増え続けています。
平均的な指定整備工場の月間入庫台数は100台を大きく下回ります。当社は170台ですから、かなり善戦していると言えます。
車検の顧客ニーズは、「技術信頼」「価格」「利便性」です。顧客との人間関係は、その後です。
道路運送車両法が改正され、ユーザー車検の代行が解禁されたのが、1995年。同じ年にSS運営を始めた当社は、いち早く車検を取り扱いました。
以来、商圏内の整備工場やカーディーラーを常に意識し、USPを与え続けてきました。
元売会社の車検ブランドや、短時間立ち会い車検を謳うFC加入も検討しましたが、やはり「お仕着せ」車検ではUSPを維持するのが困難です。
当社のUSPは「価格」です
基本料金(手数料)を「1万円ポッキリ」としました。「技術信頼」に関しては、8店のうち、指定工場が4カ所、認証工場が4カ所。40名を超る整備資格者を配備し、法定点検以上の項目を点検します。
「利便性」に関しては、当店はあまり良くありません。車検をご注文いただいたら、まずご来店いただきます。車を点検し、その結果を報告し、整備を受注します。
そして約1週間後、再びご来店いただきます。車を預かり、整備、点検、検査が完了するのは翌日の夕方となります。したがって都合3回、お客様にご来店いただいています。納車引取りは有料で対応しますが、ほとんどニーズがありません。
さて、車検は、強力なUSPを商品に付与するだけでは足りません。これをアピールすることに、かなりの人手とお金を投入してきました。
昔は、折り込み広告が主流でしたが、今は、SS利用客にLINEで毎月アピール(8店で11万件)、商圏内に毎月ポスティング(同20万件)、さらに、車検満了が近い方にはダイレクトメール(同1.2万件)、商圏内ミラーリング(同2万件)、給油で来店されたお客様には、車番認識システムを活用して人的アプローチを実施します。
加えて、インターネット広告でホームページヘの誘導、コールセンターという受注体制も運用しています。
車検1件を獲得するための販促費(CPO)は約1万円です。基本料金分が吹き飛んでしまうコストです。しかし、時間をかけて丁寧に車の状態(点検結果)をご説明して整備を提案しますので、1台当たり4万円の粗利を獲得できています。
ただ車検は、商圏内競合企業との根比べです。相手は大企業ではありません。われわれとさほど運営力が変わらない町のクルマ屋さんーだと思うからこそ、根性で戦い続けていられます。
気を抜かずにやり続ければ、いつかは地域ナンバーワンになれるかもしれない、「苔の一念岩をも通す」の思いでやっています。
その結果が、年間入庫台数1万7,000台というわけです。
SS車販のUSPはいまだ見つからない
車販のUSPには苦労しています。
中古車販売に対する顧客ニーズは、「品質」「価格」「品揃え」。
当社の今の車販の主流は、中古車を仕入れて販売するスタイルです。2020年のコロナ禍をきっかけに始めました。
市中の中古車屋さんとの違いは、中古車展示場を持たない(持てない)ことです。
店の周りの裏通りの土地を借り、ここを在庫置き場とし、ネットが集客したお客様の希望に合わせ、その都度、店先に出しています。
このハンデは、ハナから覚悟していたことです。せめて、われわれが特徴を打ち出せるとすれば、品質保証、アフターサービス、ガソリン割引くらい。ただそれだけでは、弱小中古車店には勝てるかもしれませんが、ズバ抜けることはできません。
おそらく1店当たり月間25台くらいで頭打ちとなるだろう。ならば、年間6,000台(月間500台)を売るには、20のお店が必要だ。よしっ 、さっそく元売会社に打診しよう・・・とした矢先です。
当時の菅総理大臣が「カーボンニュートラル宣言」を打ち出しました(2020年10月)。
慌てました。SSが座礁資産となってしまう事態を、生々しく想像しました。直ちに出店計画は撤回、すでに契約してしまった2店だけ、出店しました。
このとき、「年間6,000台」という計画も見直すべきでした。が、現実の車販台数は25台を超え、昨年度は29台にまで伸びました(グラフ4)。
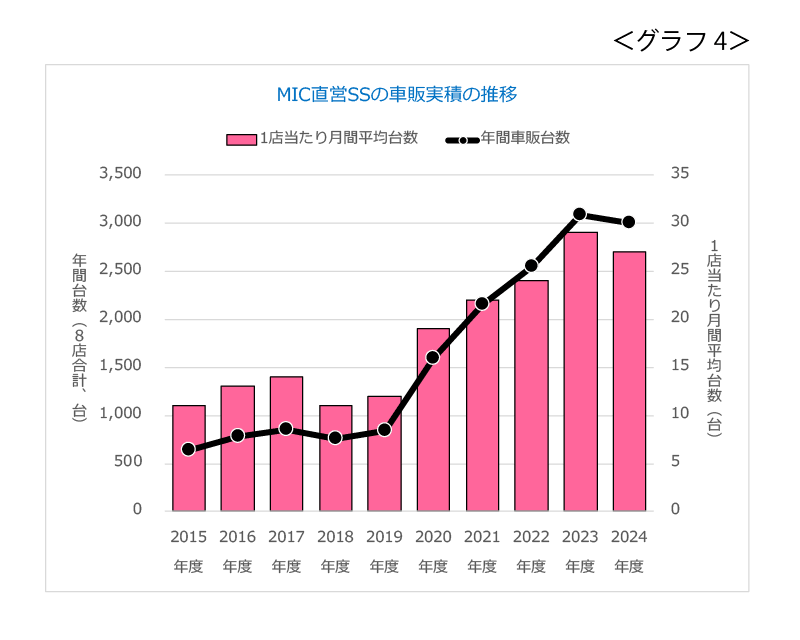
おや?もしかしたら1店25台というのは私の読み違いで、50台くらいまで行くのではないか。期待しましたが、そうは問屋が卸してくれません。
車販のUSPの強化は、今もって課題です。強力なUSPを打ち出せない以上、計画も見直さなければなりません。


